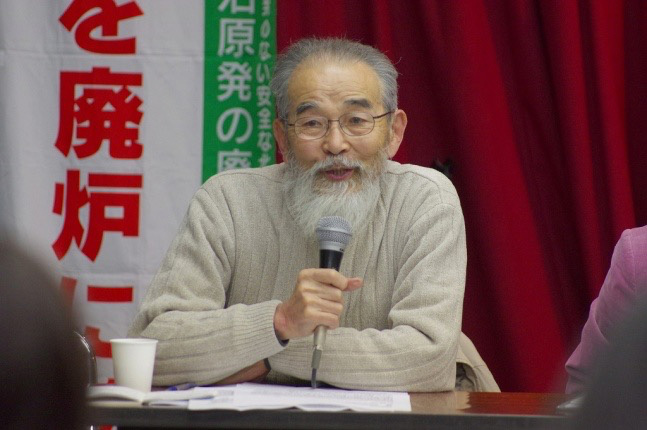
原告の一人である小林善樹です。ひと月後には81才になる元機械工学エンジニアです。1956年北大の機械工学科を卒業してから28年間函館の造船所で主に商船機関部のプラント設計に携わっておりましたから、原発の構成機器についてはそれなりの知見を持っております。
技術屋の眼から見て
2008年に札幌に引っ越し、老後を過ごすつもりでしたが、2011年の3.11事故に遭遇し、脱原発運動に邁進する途を選び、生きているうちになんとかして原発をなくしてしまいたい、との強い想いで本訴訟の原告になっております。北電の株主でもあり、リスクの大きすぎる原発は廃炉にして、原発を使わない健全な経営を目指すよう株主提案を続けております。
技術屋の眼から見て、核エネルギーを制御しながら利用する原発というシステムは、人間の手に負えるものではない、と考えています。原発は人類と共存できるものではありません。原発を制御できるなどという考えは技術者のとんでもない思い上がりだと思っています。人間は完璧な製品を作ることはできないし、製品は必ず壊れるものであり、寿命もあります。また人間は間違いを犯すものなのです。
私は子どもの頃から、「ヒトさまに迷惑を掛けてはならない」ということを信条として守って来ました。これは倫理の基本、社会生活の基本だと考えています。この考えからすると、原発という代物は全くもってヒトさまに迷惑をかけるものであり、倫理上許されざるものと言えます。ウラン鉱石の採掘現地で、精錬の過程で、濃縮・加工工場で、原発そのものの運転・整備の現場で、そして核廃棄物処理の過程で、作業員に放射線被曝を強いているのです。
原発がなくても凍死などしない
北海道では3年前の5月5日以降原発は動いてはいません。原発がなければ、電力が足りなくなるのではないか、凍死する人が出るなどとデマを飛ばした人がいましたが、三冬目のこれまで凍死した人なんかいませんでした。私は毎日発表されている「でんき予報ほくでん」のこれまでのデータを分析して、原発がなくとも、電力が足りなくなることはないと確信しています。電力料金の値上げと再値上げに触発されて省エネの気運はますます高まっていますし、来年度の電力自由化もあり、新たに参入した電力事業者からの買電も進んでおります。また、北電も、京極の揚水発電所各20万kWを昨年、今年と2基動かしますし、石狩港に建てる熱効率の高いLNGガスコンバインド発電各57万kWを18年、21年、28年と順次稼働させる予定です。
私たちの国、日本列島は世界にただ一つ四つのプレートがぶつかり合い、地殻変動がとっても激しい地震国、3.11の巨大地震は日本列島周辺の地殻変動が活動期に入っていることを示しており、御嶽山の噴火や、日本各地での連日の地震発生のニュースには不気味ささえ感じられます。この国の国土がいかにひびだらけ、断層だらけなのかがよくわかるテレビ映像が先日放映されていました。この国に原発を作ったことはそもそも間違いだったのだ、と考えています。
原発は地球温暖化対策となるのか
昨年5月21日に判決が出された「大飯原発3、4号機運転差止訴訟」におきましては、画期的な判決が出されたことはみなさんご承知のことと思います。「生存を基礎とする人格権は最高の価値を持つものであって、発電コストがどうのこうの、という経済問題とはレベルが違うのだ」という趣旨の判決は、司法権が独立していることを示してくれた画期的な判決と高く評価しております。
経済産業省が、「地球温暖化対策として原発は不可欠である」というようなことを考えているようですが、炭酸ガスなどの温室効果ガスの増加が主因であるとするIPCCの結論には異論を唱える学者もおります。原発は発生出力の約2倍の熱量を海に放出しているのです。100万kWの原発は200万kWという膨大な熱量で海水を加熱しているのです。これはそのまま地球を温暖化しています。また、ウラン鉱石採掘、輸送、精錬、濃縮、加工の各過程で化石燃料を燃やし、炭酸ガスを放出しているのです。原発は地球温暖化対策にはならないのです。
原発はいったん事故を起こすと、山も、森も、川も、海も、放射能で汚染してしまうのです。
私の子どもたちへ
先月亡くなったフォークシンガーの笠木透さんが93年に作詞・作曲された「私の子どもたちへ」という感動的な歌があります。3.11の事故後まもなく4年にもなるというのに、福島の子どもたちが今もまだ外を駆け回ることができない状況を知るいま、その3番の歌詞は、原発を容認して来た私たちの心にぐさりと突き刺さる想いがします。紹介しますと、
生きている君たちが、生きて走り回る土を
あなたに残しておいて、やれるだろうか、父さんは
目をとじてごらんなさい、山が見えるでしょう
近づいてごらんなさい、コブシの花があるでしょう
廃炉こそが、災害を防ぐための唯一の正しい選択肢なのです。
裁判長ならびに裁判官のみなさん賢明なご判断のほどを心からお願いいたします。

